前回まで、男性の育児休業の取得について考えてきました。
男性の育児休業の取得が少ないのは、育児休業が取りやすいかどうかという職場の環境によるのが一番の原因であると考えられますが、今回は少し違う面から見てみましょう。
下図は、子育ての負担を助けてくれる人・場所についての調査結果です。
図1:子育ての負担を助けてくれる人・場所

出典:少子化社会対策白書(内閣府)(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2019/r01webhonpen/html/b1_s1-1-6.html)
調査結果を全体的に見ると、一番割合が多いのが「配偶者(パートナー)」となっており、夫婦でお互いを頼りにしあっているように感じます。
しかし、既婚・子どもなしと既婚子どもありとで比較すると、男性の回答は大きく変わってはいませんが、女性の回答には変化が見られます。
既婚・子どもなしの女性にとって、配偶者と答えた方は85.5%いましたが、既婚・子どもありになると、60.9%まで減少します。
その分、子育て仲間が13.7%、近所の人が5.0%増加しています。
上記の間のみでのパーセンテージの移動ではないでしょうが、出産前は「夫婦で子育て」とイメージしていたけれど、実際に頼れたのは子育て仲間や近所の人だったと感じている方がそれなりにいらっしゃるのではないでしょうか。
私自身の経験としても、配偶者(パートナー)の休日に子どもを預けて用事を済ませるより、平日に子育て仲間に子どもを預けて用事を済ませるという女性が多かったと感じています。
さらに、子育ての負担について周囲で助けてくれる人・場所について、「特にない」と感じている方が、既婚・子どもなしの女性では6.8%だったのが、既婚・子どもありの女性では14.4%と7.8%も増加しています。
そして、「助けてくれる人」についてはそれなりに割合があることに比べて、「助けてくれる場所」については軒並み割合が低いです。
昨今、産後鬱のニュースも目にすることが多いです。
実際に子どもを産んでみたら助けてくれる人・場所がないと感じる女性が増加していることは、気になる部分です。
身内にしても外部にしても、「人」というのはその人自身の環境によって助けられるかどうかが変わってきます。
行政や民間の子育てサービス等、「助けてくれる場所」の充実が課題ではないでしょうか。
では、次回は、政府の子育て支援についてどう感じているのか見ていきましょう。
結婚や子育てに関する意識の調査関連記事 (まとめ:半沢まりこ)
あわせて読みたい
結婚や妊娠・出産に対する理想と現実のギャップを掘り下げる~結婚や子育てに関する意識その1~
前回までの8回にわたって『結婚をめぐる意識等』と『出産・子育てをめぐる意識等』について見てきました。 これらの調査によると、未婚者(18~34歳)の多くは「いずれ…
日本の少子化対策-結婚/子育て/幸…
どのような“出会い”があれば結婚につながるのか?~結婚や子育てに関する意識その2~ | 日本の少子化対策-…
前回の『結婚や妊娠・出産に対する理想と現実のギャップを掘り下げる~結婚や子育てに関する意識その1~』に引き続き、再度、結婚を希望している者で結婚していない20~40…
あわせて読みたい
出会いが少ない。では、出会うためにしていることって?~結婚や子育てに関する意識その3~
前回の『どのような“出会い”があれば結婚につながるのか?~結婚や子育てに関する意識その2~』では、“出会い”について、データから考察してみました。 お付き合いや結…
あわせて読みたい
結婚相手との理想の出会いと実際の出会い~結婚や子育てに関する意識その4~
前回は、出会うためにしている具体的な相手を探すための行動についてデータを見てみましたが、「特に何も行動を起こしていない」という回答が一番多いという考えさせら…
あわせて読みたい
理想の年収から見た結婚相手に求める条件~結婚や子育てに関する意識その5~
『結婚や子育てに関する意識』について、その2から前回までは、“出会い”に注目してデータを見てきました。 今回は、『結婚や妊娠・出産に対する理想と現実のギャップを…
あわせて読みたい
相手に求める年収、理想と現実のギャップはどれくらい?~結婚や子育てに関する意識その6~
前回は、『結婚相手に求める条件(理想の年収)』から、また経済面に着目して結婚に対する意識を見てきました。 『結婚や子育てに関する意識』シリーズのその2~4で見…
あわせて読みたい
結婚後は共働きか専業主婦・主夫か…どんな働き方を考えている?~結婚や子育てに関する意識その7~
前回までは、結婚に至るまでの出会いやきっかけ、条件などについて考えてきました。 今回からは、結婚後の働き方と家事・育児について見ていきましょう。 下図は、結婚…
あわせて読みたい
結婚後の働き方は経済面重視?精神面重視?~結婚や子育てに関する意識その8~
前回、結婚を希望している者で結婚していない20~40歳代の男女に聞いた結婚後の働き方についての調査結果をもとに、その理由を考察しました。 今回は、実際の結婚後の働…
あわせて読みたい
思いと現実とのギャップを感じる家事・育児の役割~結婚や子育てに関する意識その9~
今までは夫婦に関する話題で考えてきましたが、今回は子どもも含めた家族の話題です。 家事・育児をテーマにいろいろと考えていきましょう。 下図は、未婚・既婚子ども…
あわせて読みたい
自由時間が増えたら家事・育児の時間はどう変化する?~結婚や子育てに関する意識その10~
前回は、「家庭での家事・育児の役割は夫と妻どちらか」について、男性と女性のそれぞれの考えについてデータを見てきました。 男女ともに「妻も夫も同様に行う」を理想…
日本の少子化対策-結婚/子育て/幸…
男性の育児休業取得率はどうして低い?~結婚や子育てに関する意識その11~ | 日本の少子化対策-結婚/子育…
前回は、『家事・育児に費やす時間』について考えました。 自らの家事・育児に費やす時間の評価については、データで見ると思うところはありますが、日本の現状を考えると…
あわせて読みたい
育児休業を取りたいと思うかどうかの男女差~結婚や子育てに関する意識その12~
前回のデータでは、自由時間が増えたら家事・育児の時間も増えると思うけれども、現実的には周囲が忙しすぎて育児休業を言い出せる雰囲気ではないと感じている男性が多…
あわせて読みたい
子育ての負担を助けてくれるのは誰?どこ?~結婚や子育てに関する意識その13~
前回まで、男性の育児休業の取得について考えてきました。 男性の育児休業の取得が少ないのは、育児休業が取りやすいかどうかという職場の環境によるのが一番の原因であ…
あわせて読みたい
政府の子育て支援…足りてる?~結婚や子育てに関する意識その14~
出産し、子育てしていくには、人的資源や経済力が影響してきますが、それらを補うのが政府の子育て支援です。 前回の記事『子育ての負担を助けてくれるのは誰?どこ?』…
あわせて読みたい
政府の子育て支援への取り組み、足りていないのは何か?~結婚や子育てに関する意識その15~
政府の子育て支援の取り組みへの評価について、前回、調査結果とともにその理由を見てきました。 今回は、もう少し掘り下げて、質・量が十分でないと思う取組について見…
あわせて読みたい
安心して希望通りに子どもを持つには~結婚や子育てに関する意識その16~
前回まで、政府の子育て支援への取り組みを見てきましたが、では、さらにどのような取り組みがあれば、安心して希望通りに子どもを持とうと思えるのでしょうか。 下図は…

















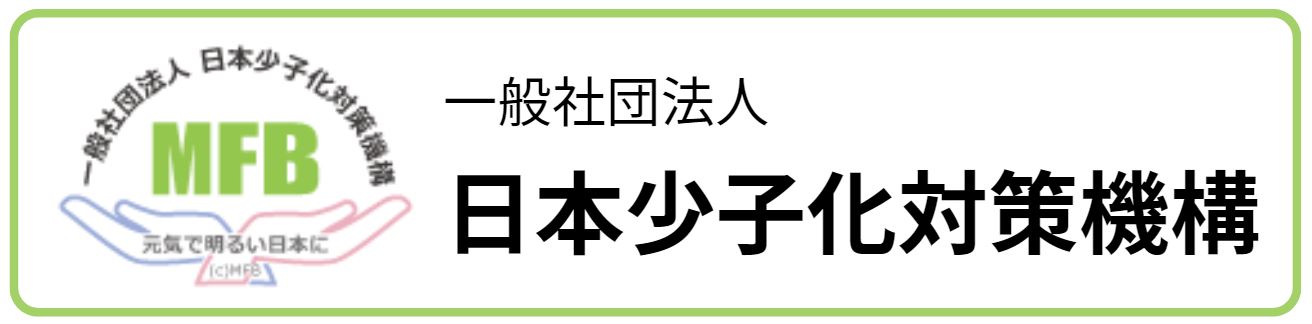







コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 前回の記事『子育ての負担を助けてくれるのは誰?どこ?』でご紹介した子育ての負担を助けてくれる人・場所の調査結果では、政府の子育て支援は上位に挙がっていませんでした。 […]